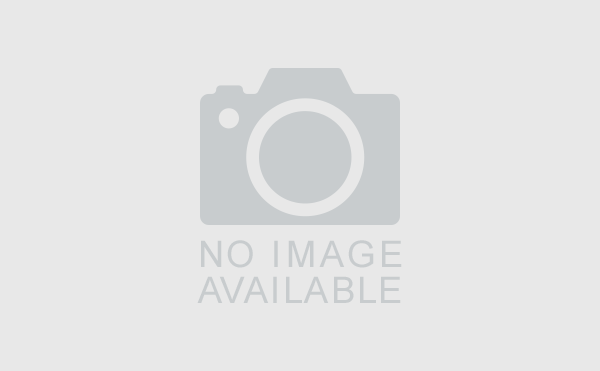ゆりもとFP直伝!家計見直し術【第9のワザ】めざせ!マイホーム取得!を成功させる秘訣 その4
ファイナンシャル・プランナー ゆりもとひろみ
前回のワザ「10年間は『満足』が続く住まいを選ぶ」で、長く満足できる住宅購入のためのライフイメージが少しずつ固まってきたのではないでしょうか。
今回は、実際に住宅を購入する際に欠かせない「住宅ローン」について、安心できる組み方をお話しします。
【第9のワザ】
住宅ローンは「返せる額」で組む
住宅を購入する際に、不動産業者や銀行から提示されるのは「年収から計算した借りられる金額(借入限度額)」です。
物件をいくつも見て回るうちに、どうしても「少しでも良いものが欲しい」という気持ちが強くなり、つい限度額いっぱいまで借りたくなるものです。
しかし、年収が同じであっても、実際に「返せる額」は家庭によって異なります。子どもの人数や希望するライフスタイルによって、住居費に充てられる金額は変わってくるはずです。
では、無理のない借入額はいくらなのか?
35年ローンを組むなら、35年間の資金の流れをシミュレーションし、
- この先、どれくらい収入が入り、どれくらい支出が出ていくのか
- そのうちローン返済に無理なく充てられる金額はいくらなのか
を計算しておく必要があります。これを怠ると、常に不安を抱えたままの生活になりかねません。
たとえば「保険」は、解約すれば保障はなくなる代わりに支払いをやめられます。しかし「借金」は、嫌になっても支払いをやめることはできません。
世帯主の収入ダウンや、出産による奥様の収入減少といった可能性も考慮し、無理のない範囲に借入額を抑えることが、不透明な時代において重要な安全策になります。
ローンを負担する人は誰?
さらに注意したいのは、返済に協力する家族がいる場合です。その方にも「死亡保険」や、場合によっては「所得補償保険」を用意しておくことが賢明です。
実際に、あるご家庭では同居するお姑さんの収入を見込んで高額なマンションを購入しました。しかし、お姑さんが1年後に病気で亡くなり、奥様は小さなお子さんがいるためすぐに働きに出られず、重い返済負担に苦しんでおられます。
購入時にお姑さんも保険加入していれば、避けられたピンチでした。
事故や病気、収入減といったアクシデントがあっても、家を手放さずに済むように、計画的な返済プランと保障の準備を整えてから住宅ローンを組むことが大切です。
借りてから「しまった!」と後悔しないように。少しでも不安を感じる方は、あなたの立場で考えてくれる専門家に早めに相談されることをおすすめします。
このコラムを書いた人
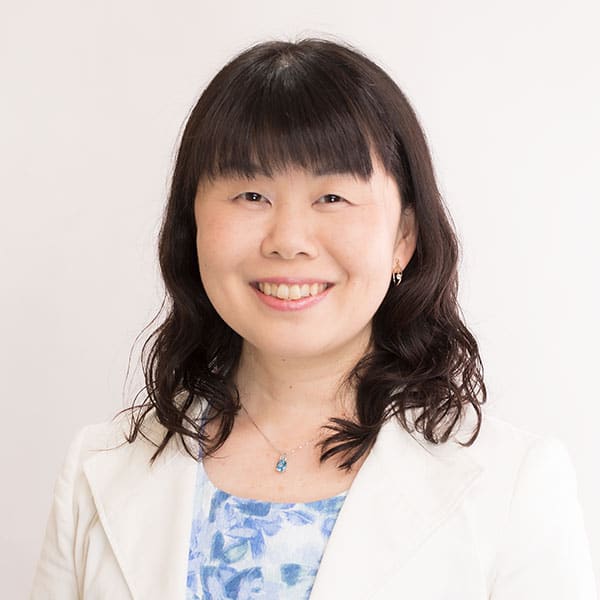
ゆりもとFP事務所 代表
株式会社FPフローリスト 代表取締役社長
圦本 弘美
ゆりもと ひろみ
ファイナンシャル・プランニングで
日本を元気にします!
- CFP®認定者
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
- 一種外務員