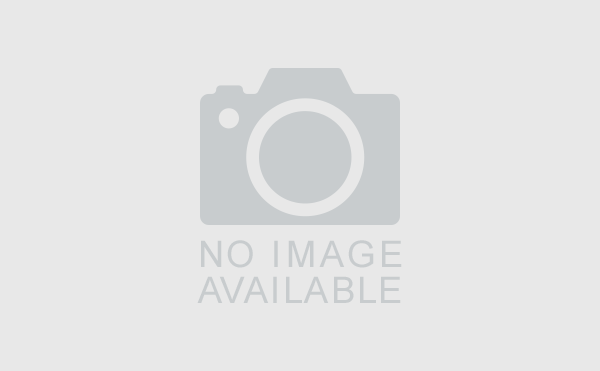ゆりもとFP直伝!家計見直し術【第17のワザ】一家の経済危機を乗り越える秘策 その1
ファイナンシャル・プランナー ゆりもとひろみ
自殺の原因の第2位は「経済・生活問題」
厚生労働省と警視庁の統計によると、令和6年の自殺者数は20,320人でした。ここ数年は減少傾向にあるものの、依然として毎年2万人を超える人が自ら命を絶っている状況が続いています。平成中期のピーク時には、年間34,427人にものぼりました。
かつては「自殺者が3万人」と言われていましたが、これは人口36万人の都市が12年で空になってしまうほどの数です。平和なはずの日本で、深刻な事態が長年続いてきたことを示しています。
自殺の原因の第1位は「健康問題」、そして第2位が「経済・生活苦」です。
ファイナンシャルプランナーとしては、「経済・生活苦」による自殺やその予備軍を救う方法を何とか編み出したいと強く願っています。
そこで今回と次回は、破産や自殺といった窮地に陥らないために必要な対策についてお話しします。
お金は人生を支えるエネルギー
お金は、人生をよりよく生きるための大切なエネルギーです。上手に使えば夢を実現する力を持ちますが、使い方を誤れば人生に致命的なダメージを与えることもあります。
それでも忘れないでいただきたいのは、どんな時でも「一番大切なものを見失わないこと」です。
かつて、自殺で父を亡くした子どもが書いた文章を読み、胸を打たれたことがあります。
その少年はこう訴えていました。
「僕は、どんなに貧乏でも、どんなに苦労してもいいから、お父さんに生きていて欲しかった」
あなたが今つらくても、みじめに思えても、生きているだけで守れるものがあり、喜んでくれる人が必ずいます。ぜひそれを信じて、人生を立て直す道を探してみてください。
日頃から家計の転覆を防ぐ工夫を
収入が大きく減り、住宅ローンや教育費の支払いが行き詰まることは、誰の身にも起こり得ます。日頃から備えておけば、大きなダメージを防げたはずなのに…というケースも少なくありません。
家計も生活習慣病と同じで、発病(破綻)してから立て直すより、予防のほうが何倍も低コストで済みます。ただ、兆候が出ている段階で思い切った対策を取るには、勇気と覚悟が必要です。
それでは、第17のワザをお送りします。
【第17のワザ】
現実をありのままに見る勇気を持つ
「現実」とは、つまり家計の現状を直視することです。
毎月・毎年の収支を把握し、教育費の見通しや住宅ローン金利上昇時の影響など、将来の収支まで冷静に見積もる必要があります。
しかし、家計が厳しいほど「見たくない」という心理が働き、放置してしまうケースが多いのです。その結果、傷口が広がってしまいます。
現実を見られず対策を取れない人には、大きく2つのパターンがあるように見受けられます。
パターン(1):人任せ・運任せの考え方
「いざとなったら親が助けてくれるはず」「いざとなったらローンを組めばいい」といった、人任せ・運任せの姿勢です。
もちろん、親からの援助をきちんと仕組み化できる家庭は立派です。しかし、「人のお財布」や「未来のお財布」を当てにしてしまう習慣は、ある種の甘えやだらしなさにつながります。
この甘さを改め、現実を受け止めて少しずつでも改善していこうと決意しない限り、経済的危機は繰り返し襲ってきます。
一方で、どんなに厳しい状況でも「自分の責任で対応しよう」と勇気を持って行動する人には、前向きなエネルギーが宿り、精神的に引き締まった美しささえ感じられます。そうした方には、私も心から応援したくなります。
甘えを捨て、生活コストを正確に計算し、収入の範囲で支出を管理すること。月に千円でも黒字を出すことを続けていけば、小さな歩みでも必ず成功へ近づいていけます。
現実を見られないもうひとつのパターンについては、次回で詳しくお話したいと思います。このパターンの方は、自力で家計のリストラができず、深刻な事態を招きやすいのです。
キーワードは「恐怖心」です。
一家の経済危機を乗り越える秘策 その2 へ続く
このコラムを書いた人
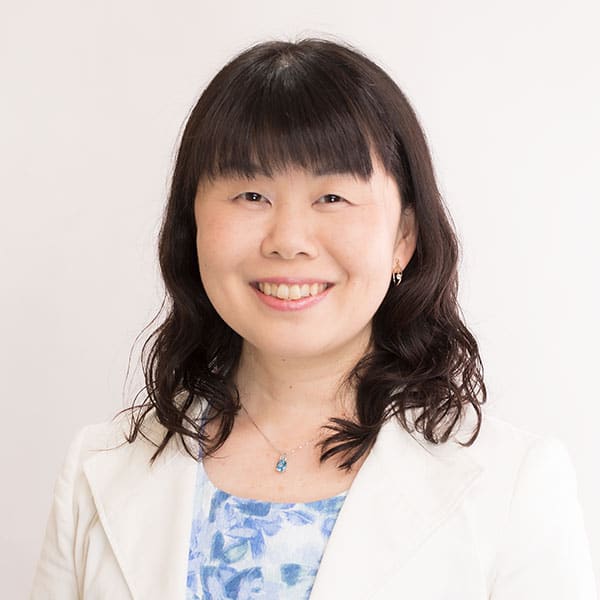
ゆりもとFP事務所 代表
株式会社FPフローリスト 代表取締役社長
圦本 弘美
ゆりもと ひろみ
ファイナンシャル・プランニングで
日本を元気にします!
- CFP®認定者
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
- 一種外務員